多くの山岳地帯が連なる日本列島。山地や丘陵地は国土の約7割を占め、古くから人々に身近な自然として親しまれてきました。山の名前には「富士山」のように「山」とつくものだけでなく、「岳」や「峰」といった表記もあります。これらの違いにはどのような意味があるのでしょうか。
もっとも一般的な呼び名が「山」
「山」「岳」「峰」といった呼び分けには、標高や地形による明確な定義はありません。ただし、それぞれに込められたニュアンスや使われ方には一定の傾向があります。
「山」とは、周囲より高く盛り上がった地形や場所のこと。地形学的には、起伏量が数百メートル以上で構造が複雑なものを指します。「しっかりとした起伏」「明確な山頂」「独立した山塊」といった特徴を持つ地形に用いられるのが「山」という表記です。
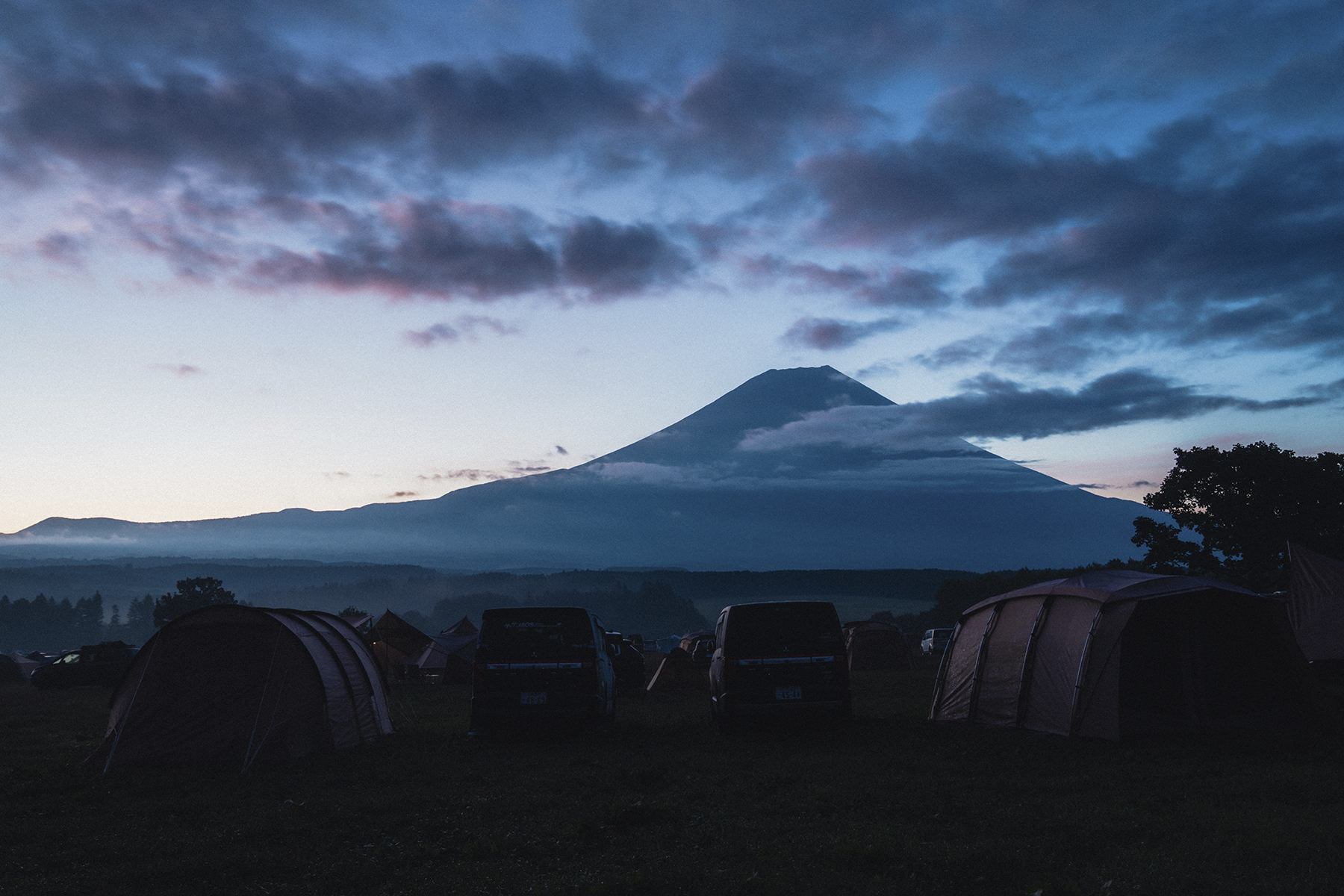
例えば「富士山」や「筑波山」は独立した山塊であり、「山」と名付けられる典型例と言えるでしょう。
険しさと威厳を示すのは「岳」
「岳」は、「山」の上に「丘」を重ねた字形からもわかるように、高く険しい山を思わせます。「槍ヶ岳」や「八ヶ岳」のように標高が高く、ごつごつした地形や峰々が連なる場所に用いられることが多い漢字です。

ただし、鹿児島県の「開聞岳」のように、独立した山塊でありながら「岳」と名付けられている例もあります。「山」と「岳」の使い分けには例外が多いものの、荒々しく厳しい自然を感じさせる名称として用いられる傾向があります。
山頂や尾根を示す「峰」
「峰」はもともと「山の高いところ」という意味を持つ言葉。山全体ではなく、山頂や尾根、あるいは連山の中で一つのピークを表す名称としてよく用いられます。
代表例が長野県の「霧ヶ峰」。車山を主峰とする標高1500~1900メートルの高原地帯で、緩やかな起伏が続く場所です。グライダーの飛行にも適しており、開放的な風景が広がります。

また「最高峰」や「連峰」といった言葉からも、「峰」が山の特に高い部分を示す語であることがわかります。
このように「山」「岳」「峰」の呼び方には厳密な基準はないものの、自然の印象や地形の特徴を映した名称が多く見られます。「岳」や「峰」という名を見かけたときは、どのような地形を指しているのかに注目してみると、新たな発見につながるでしょう。

 記事一覧
記事一覧 キャンプ場を探す
キャンプ場を探す ショッピング
ショッピング












