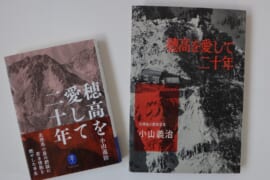貴重な水は「天水」と呼ばれて大切にされている
登山用語で、雨水のことを「天からの恵み」という意味で、「天水」と呼びます。水場がない小屋では、降った雨をドラム缶や大型タンクなどに集めて利用しています。穂高岳にある穂高岳山荘は、奥穂高岳と涸沢岳の間の白出コルという狭い場所に建っています。

岩ばかりの山のコル(峠)なので、小屋の近くに沢もないし、湧き水もありません。そこで、北側の涸沢岳東面にある雪渓を夏の間の水源として利用しています。急峻で脆い岩壁を伝って、200mも先からホースを使って導水しています。その設置作業は決して容易ではなく、毎年水源を掘り出す作業は三日ほどかかるそうです。
穂高岳山荘では、この水のことを「天命水」と呼んでいます。今年も6月の末に、無事作業を終えられたもよう。雪渓が消えるまでの間はとりあえず安泰です。しかし、雪渓に頼っている場合、雪解けが早ければいずれ水不足になる可能性があります。また、元々天水に頼らざるを得ない立地の小屋では、日常的に水は不足しがちで、いろいろと苦労されています。
水に恵まれた小屋では、そのまま飲める水を水場で流しっぱなしにしていたり、もちろんそれは汲み放題だったりもしますが、水源が乏しいところでは、水は有料です。小屋によりますが、概ね500mlで200円くらいでしょうか。

トイレでうっかりやってしまいがちなNG行為
日常生活では、どこに出かけようが水洗トイレがあると思うのですが、上下水道がない山小屋では、トイレは当然水洗方式ではありません。立地によってトイレのスタイルはいろいろで、あまり標高が高くないところでは、快適なバイオトイレが設置されているところもあります。おがくずなどを使って、微生物の力でし尿を分解するしくみで、匂いもほとんどありません。
それに対して、日本アルプスなどの高い山にある小屋では、まだ汚物はタンクにためてヘリで空輸する方式が主流。そこで注意が必要なのが、使用した「紙」の問題です。
運搬する量を少しでも少なくするために、トイレットペーパーは別に回収する方式のところがほとんどです。個室内にトイレットペーパーの回収ボックスが置いてあって、使用した紙はそこに入れることになっているのですが、頭でわかっていても、つい習慣でポイっとしてしまいがちなのです。気をつけましょう。
また、便器にモノを落とすと、なかなかやっかいなコトになります。ポケットに入れているスマホや小銭入れを落としたという話はよく聞きます。この点にも充分注意してください。
ファスナー付きのポケットに入れてしっかり閉めたことを確認するか、仲間に預かってもらって、そもそも個室に持ち込まないようにするか。筆者はボトムスのポケットには一切モノを入れないようにしています。街の常識とは少し違うルールがいろいろとある山小屋の世界。あらかじめ知っておくとトラブルなく楽しめますよ。

 記事一覧
記事一覧 キャンプ場を探す
キャンプ場を探す ショッピング
ショッピング