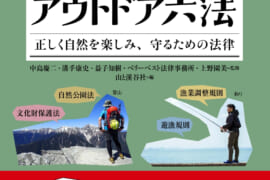登山の世界には、街中で過ごしているときとは違う、独自のルールやマナーがいろいろあります。ビギナーさんのなかには、「なんでそうなの?」という疑問を持つ人も少なくないでしょう。そんな〝山のルールやマナー〟に関して、素朴な疑問なども含めて解説します。今回は、「あいさつ」について。
家の近所で、近隣住民の人と顔を合わせるとあいさつはしますよね。
でも、街中ではどうでしょう。知り合いはべつとして、見知らぬ人にあいさつをすることはまずありません。いきなり知らない人から「こんにちは」なんて話しかけられたら、びっくりしてしまいます。
「見知らぬ人に用もないのにいきなり話しかけたりしない」は、都会での暗黙のルールではないかと思います。でも、山の中では見知らぬ者同士、会えばあいさつを交わすのが〝お約束〟なのです。

山は恐ろしい場所だから?
そもそも挨拶を交わすという行為には、お互いに「自分は怪しいものではありません。アナタに対して害意はありません」ということを示すためのもの、という意味があります。中世頃まで、日本では遊びで山に入る者はほとんどいなかったそうです。
〝おじいさんがしば刈りに行く〟ような、村から近い里山はべつとして、深い山の奥には、マタギなど山を仕事場にしている人々か、修験道など山岳修行の人々、そしてやむを得ず山越えで移動する人々くらいしか足を踏み入れることはなかったのだとか。
そして屈強なマタギや修験者はべつとして、山慣れしていない一般人は、追剥ぎに襲われたり、魔物に憑りつかれたり(?)して、山中で命を落とすことがけっこうあったという話が各地で伝えられています。筆者のホームマウンテン六甲山には「シュラインロード」という道があります。
かつてこの道で山越えをした人たちが、追い剥ぎに襲われたのか魔物に出遭ったのかはわかりませんが、山中で命を落とすことが時々あって、そのような人々の供養のために、山麓の村人たちが石仏を祀ったそうです。

同じ六甲山地で、古くから「烏原越」と呼ばれていた古道沿いには、「南無阿弥陀仏」の文字が刻まれた岩があり、「名号岩」と呼ばれています。これも、この道で命を落とした人々の霊を慰めるため、近くのお寺のお坊様が刻んだものと伝えられています。

山は恐ろしい場所なので、誰かに会ったらとりあえずあいさつをして、お互いに安心したのではないでしょうか。
登山者同士のあいさつのルーツは?
日本の近代登山は、明治時代に日本にやって来た外国人たちが日本の山に登るようになったことから始まりました。のちに、「日本アルプス」の名付け親となるガウランドと、アトキンソン、アーネスト・サトウという3人パーティが、ピッケルとナーゲル(鋲靴)で六甲山に登ったのが日本における近代登山の始まりと言われています。
その後、日本人の間でも登山を志す人々が出てきますが、はじめのうちはセレブ階級の高尚な趣味、という感じだったようです。
有産階級のエリートたちが、地元の山に詳しい案内人や荷物運びの人夫を雇って、優雅に楽しんでいたそう。なので、セレブらしい礼儀としてあいさつを交わしていたのが、山のあいさつのルーツなのかも?
山でのあいさつはどんなタイミングで?
基本的に、登山道で登山者同士がすれ違うときにあいさつを交わします。「こんにちは」だけでなく、朝早い時間なら「おはようございます」ということもあります。自分の前を、ゆっくり歩いている方がいらして、追いついてしまったときも、うしろから「こんにちは」と声を掛けて、道を譲ってもらうこともあります。
また、あまり人がいないマイナールートでは、誰か来るとは思わずに、道の真ん中で休憩している人に出くわすこともあります。そんなときも、「こんにちは」の一言で気づいてくれて、道を開けてくれるでしょう。そういえば、山では早立ち早着きが基本なので、「こんばんは」のあいさつはあまりしたことがありません。


 記事一覧
記事一覧 キャンプ場を探す
キャンプ場を探す ショッピング
ショッピング